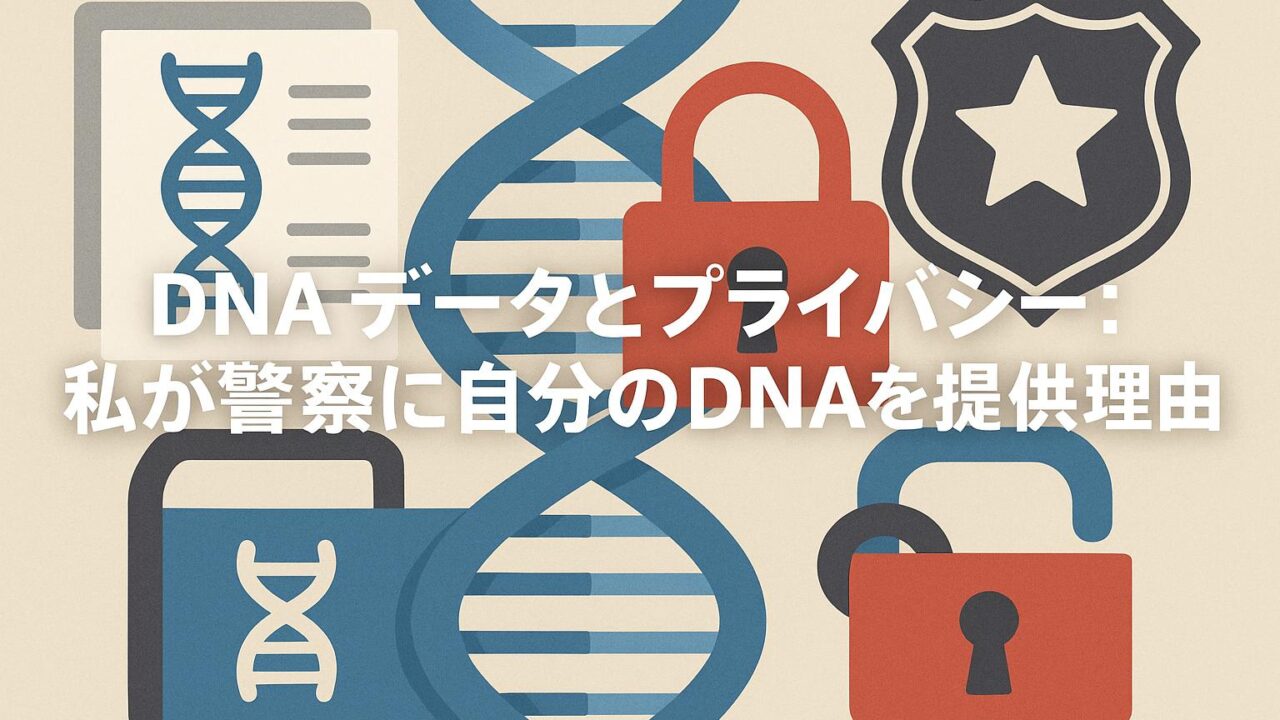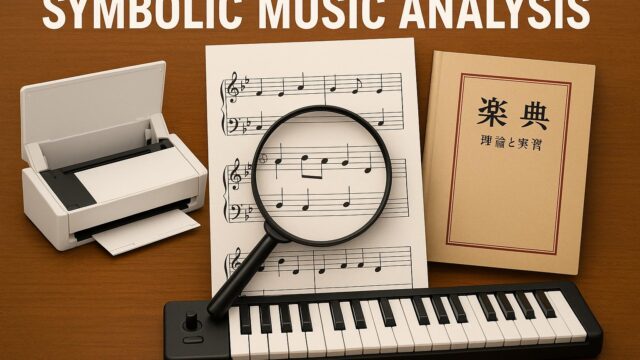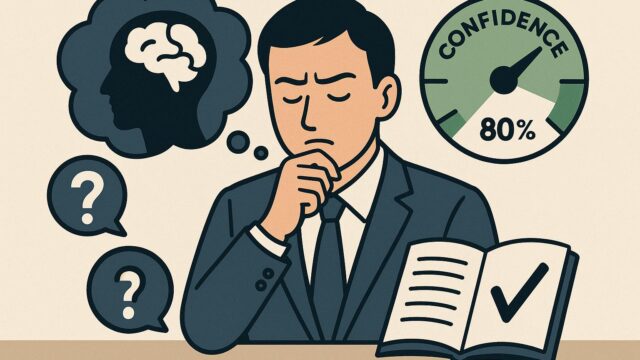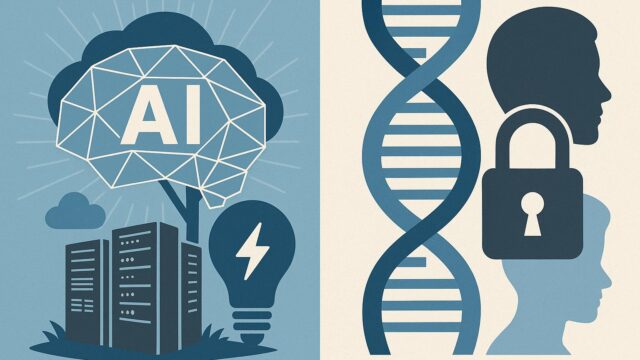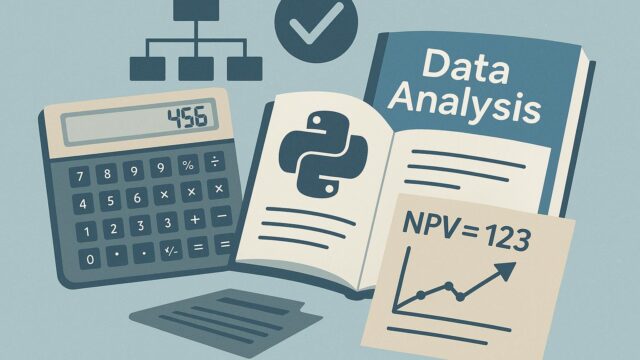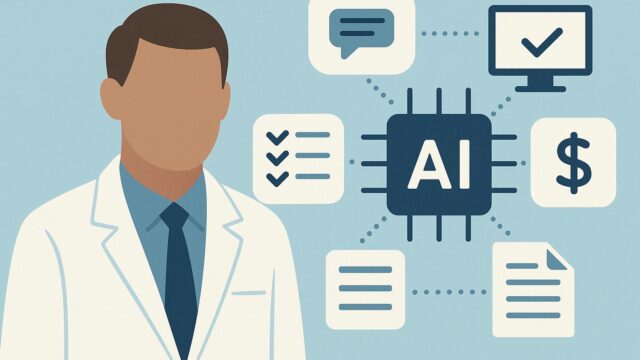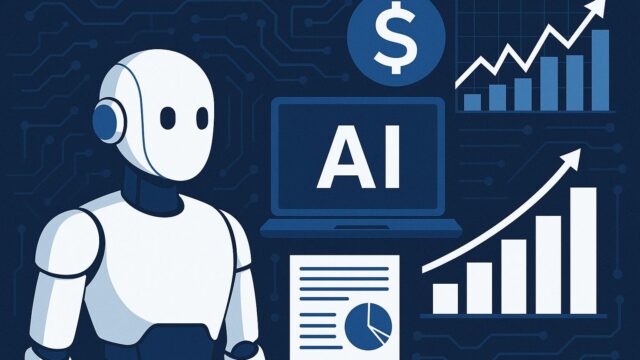DNAによる捜査協力:善意の先にある現実
個人のDNAデータは、医学や祖先探究に使われるだけでなく、近年では犯罪捜査にも利用され始めています。この記事の筆者は、自身が行った遺伝子解析サービスの結果を専門プラットフォームにアップロードし、遠い親戚を探す一環として警察がアクセス可能な状況をつくっていました。筆者は、それがどのような結果を生み出したのか、そしてそのことでどんな倫理的な問いが生じたのかを、冷静に振り返っています。
親族網と法執行のリンク
筆者が使用していたGEDmatchのようなDNA共有プラットフォームは、ユーザーが自分のDNAプロファイルをアップロードし、親戚や共通祖先を探すことができるサイトです。警察は、時にこうしたデータを利用して未解決事件の容疑者を親族経由で特定しようとします。筆者のDNAが遠い親戚の検索で一致した結果、全く知らない家族関係を通じて、他人の人生が法的に変わってしまうという事態に直面します。
人は情報の所有者なのか
このような事例が投げかける最大の疑問は、「DNA情報は個人のものであり続けるのか」ということです。あなたが自分のDNAを公開したつもりでなくとも、親族がアップロードしたことで間接的に自分の遺伝情報が利用され、公的機関にアクセスされた可能性があるのです。つまり、私たちの遺伝情報はもはや完全にコントロールできるものではないという現実があるのです。
メリットとリスク、そして選択
DNA捜査の技術は、未解決事件の解決という点で大きな成果をあげつつあります。しかし、これには明確なルールや意思表示の仕組みが必要です。多くのDNAサービスが「法執行機関へのデータ提供を許可するかどうか」のオプションを設けていますが、ユーザーがその意義を完全に理解しているとは限りません。
私たちはどうすればいいのか
筆者は、結果的に家族の誰かが予想外の形で捜査協力の線上に立たされたことにショックを受けますが、「もしそれが社会正義に寄与したのであれば良いことかもしれない」とも感じています。それが正義かプライバシー侵害かの境界は、技術が進む今こそ議論されるべきテーマです。私たち一人ひとりが、自らのDNA情報や家族の情報が持つ重みと向き合い、その在り方を考える時代に突入しています。