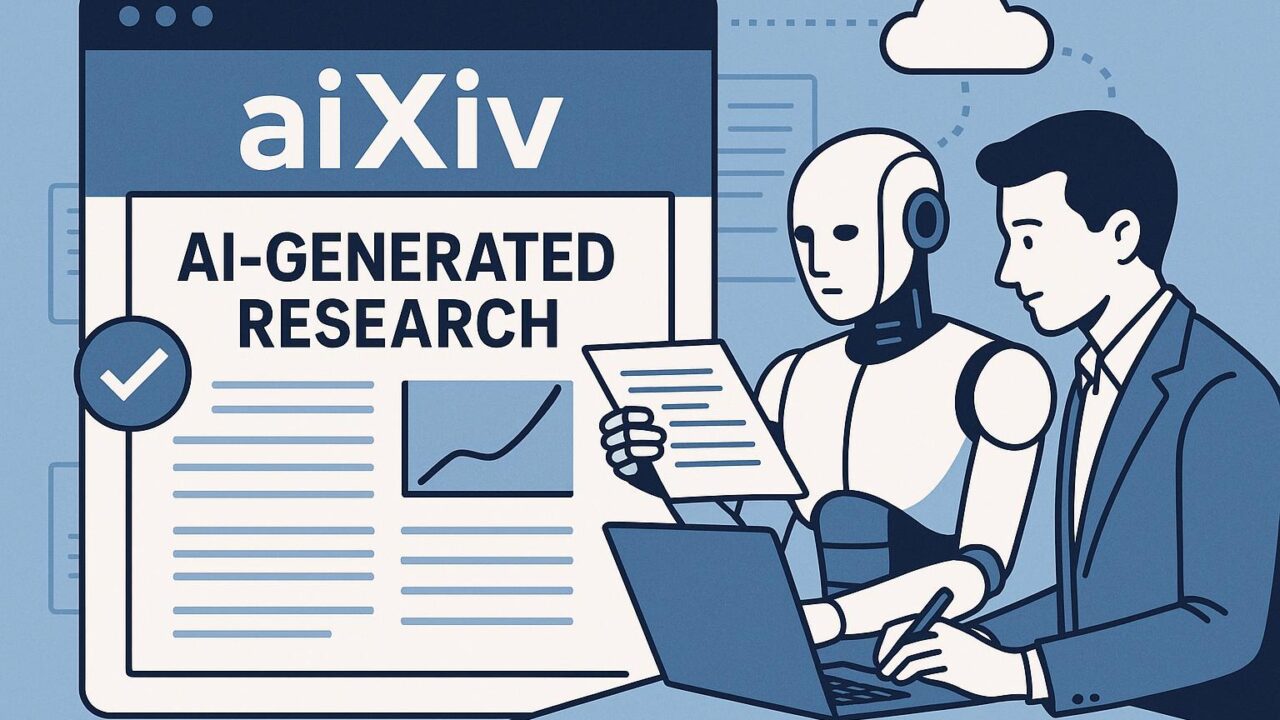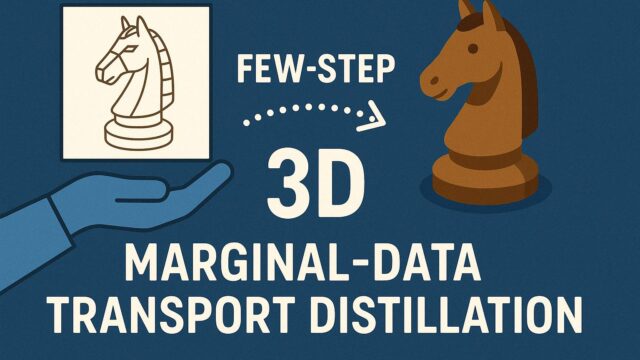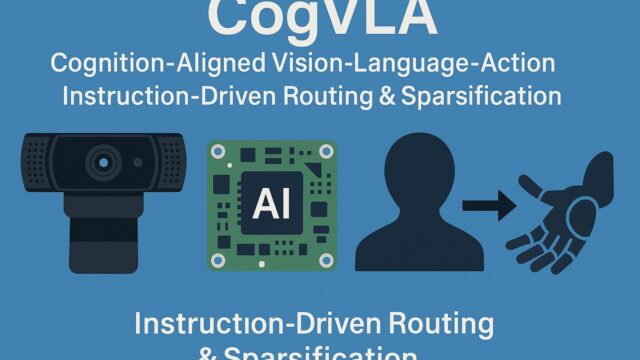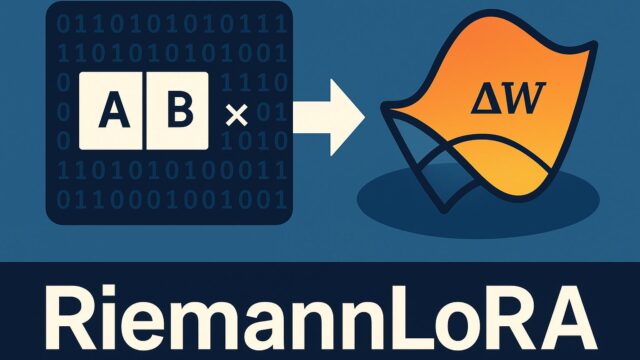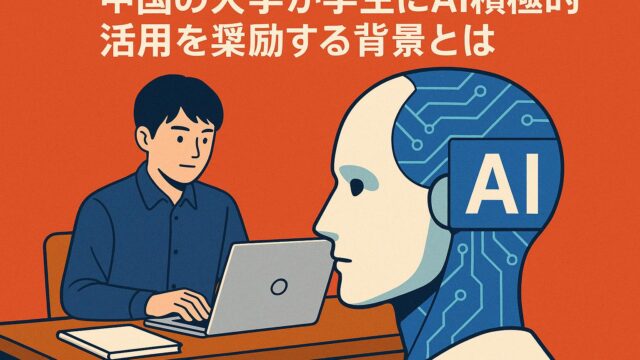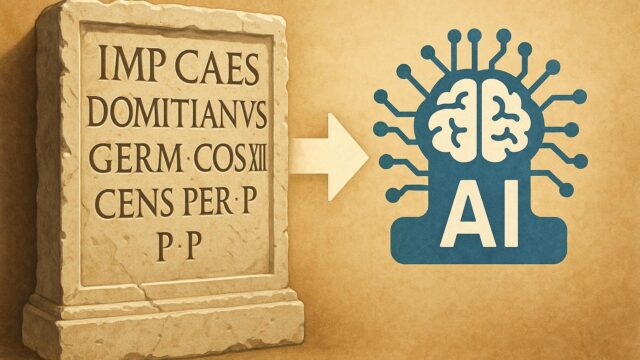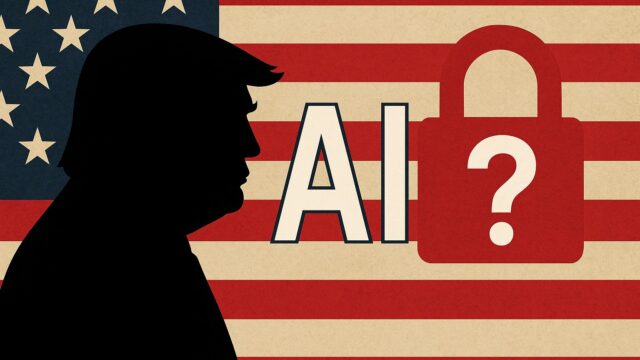序章:AIと科学の出会いがもたらす革新
急速に進化するAI技術が、科学のあり方さえも変えようとしています。特に大規模言語モデル(LLM)が、本格的に科学的発見への寄与を始めた今、「AIによる科学の自律的発展」という未来が現実味を帯びてきました。そんな中、従来のオープンアクセスプラットフォームの限界を打破し、AI科学者の登場を前提にした次世代の知識共有基盤として登場したのが、aiXivです。本稿では、aiXivの概要と可能性、そしてそれがもたらす科学研究の未来についてご紹介します。
aiXivとは何か?
aiXiv(エーアイアーカイブ)は、従来のプレプリントリポジトリにとどまらず、「AI科学者」による研究をも共有・評価できる新しいオープンアクセスエコシステムを志向しています。arXivを起点としつつも、それを拡張して、人間とAIの協働で進められる科学発見の土壌を整備しようという試みです。特徴的なのは、投稿・査読・引用・再利用など、科学の中核的なプロセスすべてにAIを自然に組み込めるような柔軟で拡張可能なシステム設計です。
現在の科学コミュニティの限界への挑戦
科学論文の急増、レビューの遅滞、非体系的な知識管理――研究者が日々直面している課題は深刻です。人間による査読のキャパシティは限りがあり、有益な研究が陽の目を見ない一方で、品質の担保が難しい情報も氾濫しています。こうした中、aiXivはAIによって科学的知識の流通と検証のプロセスを補完し、加速させることを視野に入れています。
人間とAIの協働による科学発見
aiXivが特に注目される点の一つは、「AIが作成した科学論文」が正式に投稿・管理されるという点です。これにより、単なる補助としてのAIから一歩踏み出し、AIが主体的に実験仮説を立て、シミュレーションを行い、分析結果をまとめて論文化するという構図が現実のものになりつつあります。その過程で重要となるのが、透明性、検証性、インターオペラビリティ(相互運用性)です。aiXivでは、これらを担保するメタデータ標準や査読システムの設計にも力を入れています。
aiXivの機能と構成
- モジュラー構造:投稿、査読、検索、再利用、といった機能ごとに独立したモジュールを提供
- AIフレンドリーな設計:自動生成された論文も処理できるよう、記述形式やメタデータの最適化
- 拡張性と分散性:ブロックチェーン技術などによる信頼性の担保と、脱中央集権的な知識管理
科学の未来を開く鍵として
aiXivの展開によって、研究活動の敷居が下がり、世界中の人々や、未来のAI科学者が、より広範で自由な形で科学に貢献できる可能性が開かれます。その結果、これまで見落とされていた知見が可視化されたり、人間のバイアスから解放された新たな視点で問題にアプローチできたりするのです。
まとめ:AIと共に創るオープンサイエンスの新章
aiXivは、単なる論文投稿サイトではありません。それは人間とAIとが共に科学を切り拓くための次世代インフラであり、「知の民主化」を具現化するための先進的な試みなのです。今後、研究者や学生、開発者らがこの仕組みにどのように関与し、進化させていくかによって、科学の未来は大きく変わるかもしれません。