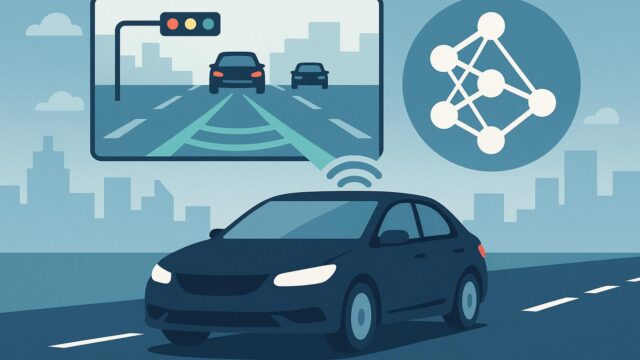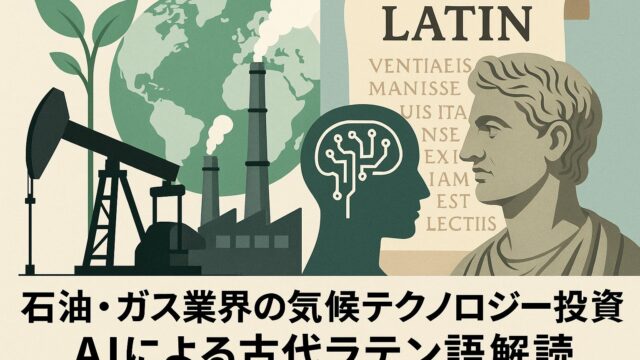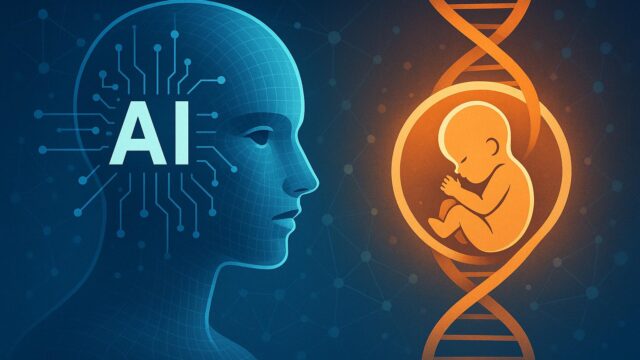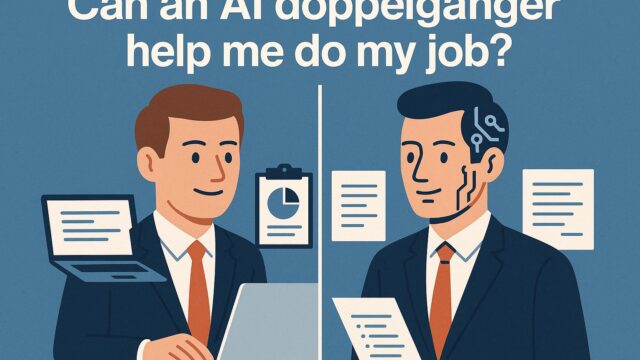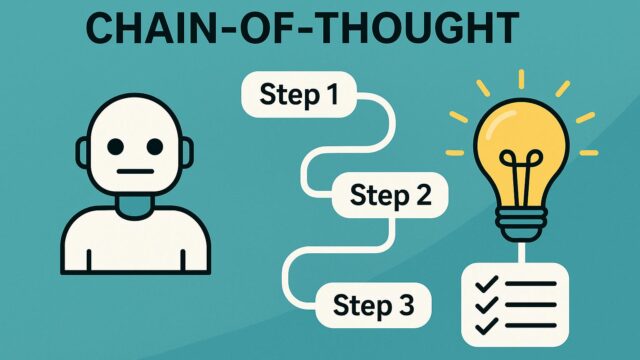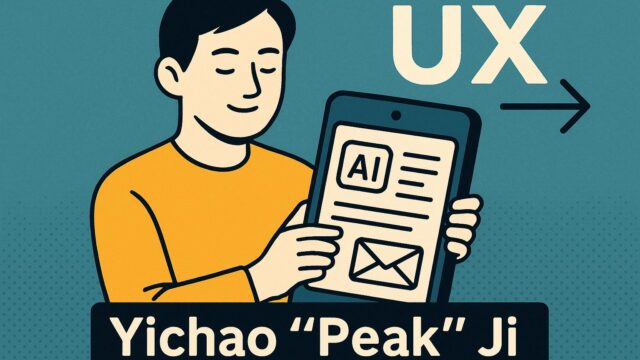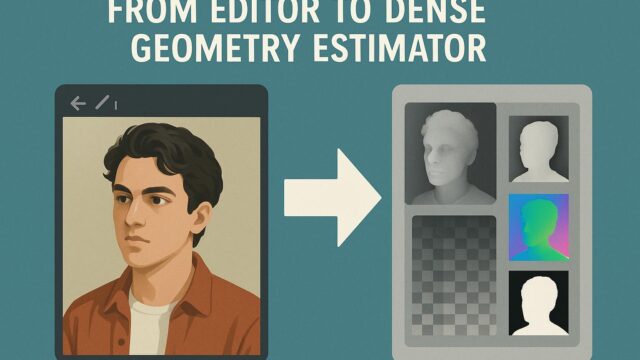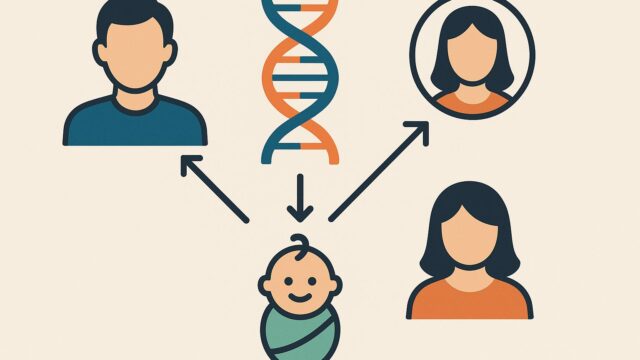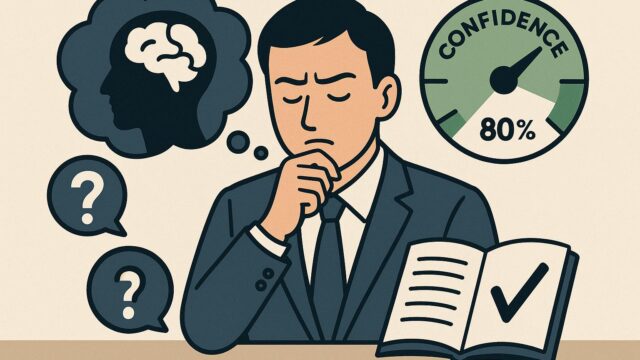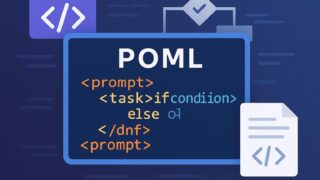建築が問い直される時代へ
建築は単なる空間のデザインではなく、環境・資源・社会との持続的な関係性を問う重要な産業分野です。従来の建築においてはコンクリートや鉄といった環境負荷の大きい素材が多用されてきましたが、気候変動や資源の枯渇が叫ばれる中、今まさに新たな価値観へとシフトする必要があります。
Material Culturesとは?
イギリスの建築スタジオ「Material Cultures」は、建築材料とその生産過程を見直し、伝統的な技術や地域の資源に根ざした建築アプローチを提唱しています。彼らのビジョンは明確です。未来の住環境は、高度に工業化された現代建築の反対を行く必要があるということ。つまり、生分解性の素材、修復可能な構造、そして地域社会に支えられた設計哲学が必要だということです。
素材へのアプローチ──「低炭素建築」の鍵
Material Culturesが注目しているのは、 ヘンプ(麻)やストロー(藁)、木材 といった、自然素材を建築に積極的に活用することです。これらの素材は二酸化炭素の吸着率が高く、製造時のエネルギー消費も少ないため、従来の素材に比べて圧倒的に環境負荷を軽減できます。
特に画期的なのが「ヘンプリート」と呼ばれる麻由来の建材です。これは調温・調湿効果にも優れており、断熱性の高い住空間を省エネルギーで実現可能にします。
過去へのまなざし──伝統的な知恵と現代技術の融合
Material Culturesは、素材の選択だけでなく、その施工手法にも持続可能性を追求しています。中世の木造建築の技術から学び、接着剤や化学合成材を使わないジョイント構造を積極的に取り入れることで、建築自体が修復や再利用可能なシステムへと変容していきます。
また、地域の土地に根差した素材や工法を推奨することで、グローバルな輸送に頼らない地産地消の建築文化を取り戻そうとしています。
建築における「倫理」の再定義
Material Culturesの視点は、建築における倫理の再定義とも言えるでしょう。単に美しい建物をつくるのではなく、環境・社会・経済すべてにおいて責任ある選択を行う。そのために素材の履歴、建築物の寿命、解体時の負荷までもが問われるのです。
このようなスタンスは、建築家やデザイナーだけでなく、利用者である私たち一人ひとりが持つべき感覚かもしれません。
未来へ向けて
Material Culturesの取り組みは、環境建築の未来に向けた強いメッセージを示しています。単なる技術的革新ではなく、素材、文化、経済、倫理――複雑に絡み合う課題を統合的にデザインすることが、これからの建築には求められているのです。
私たちが住む空間が、どのように社会や環境に影響を与えるのか。Material Culturesの実践は、その問いに対する一つの優れた答えとなり得るでしょう。