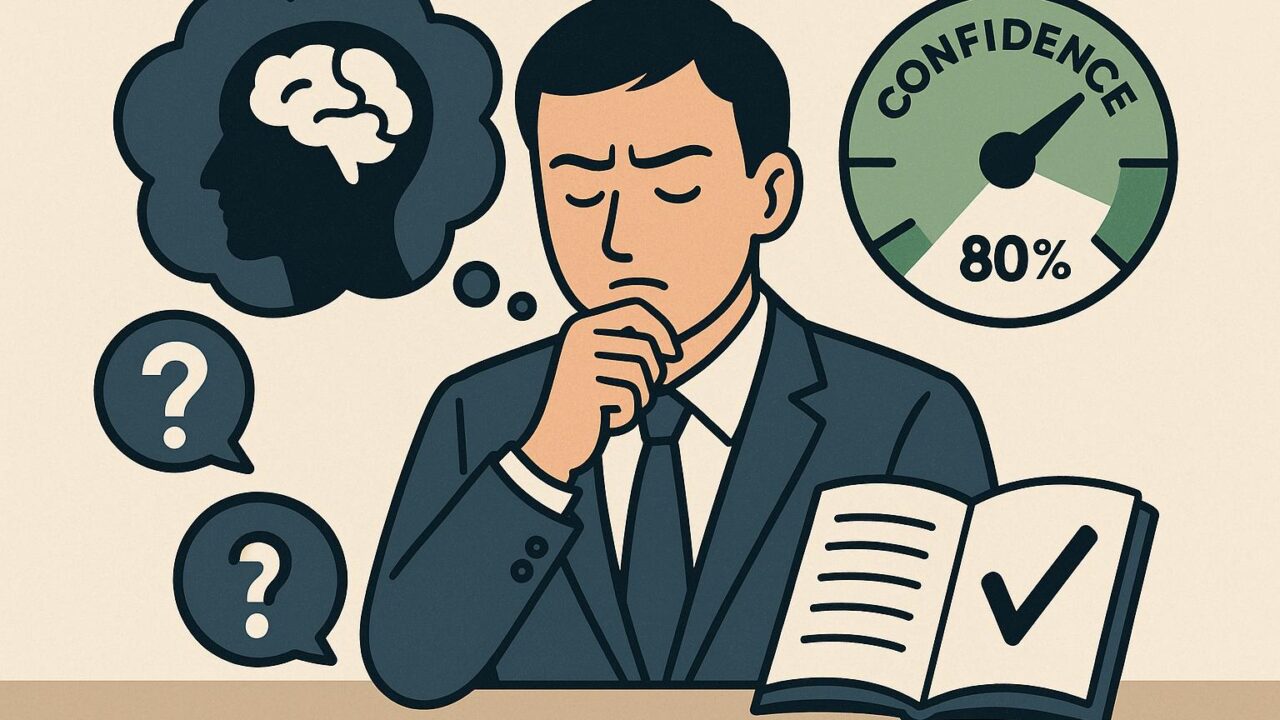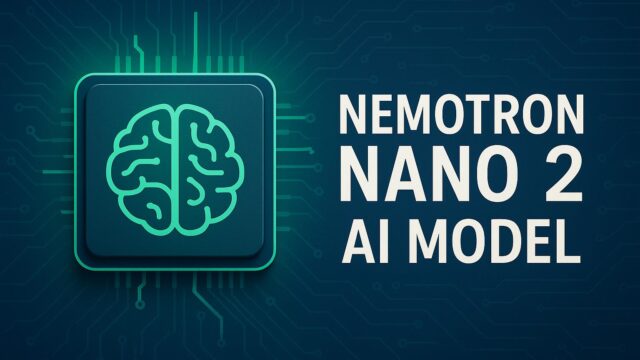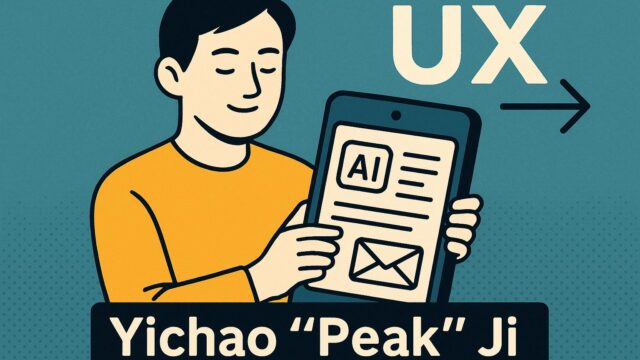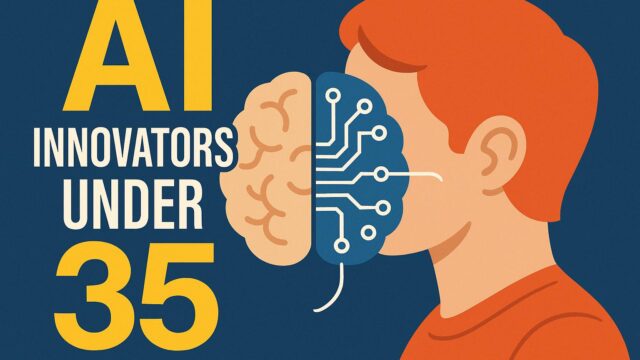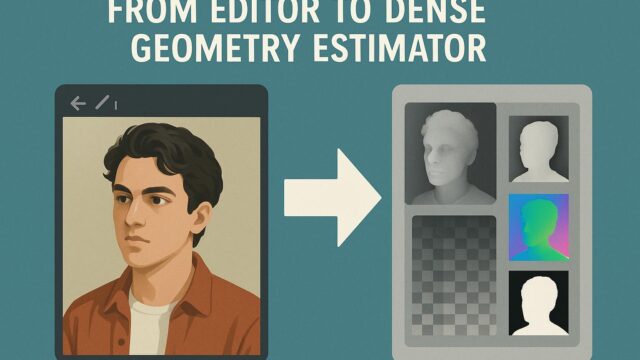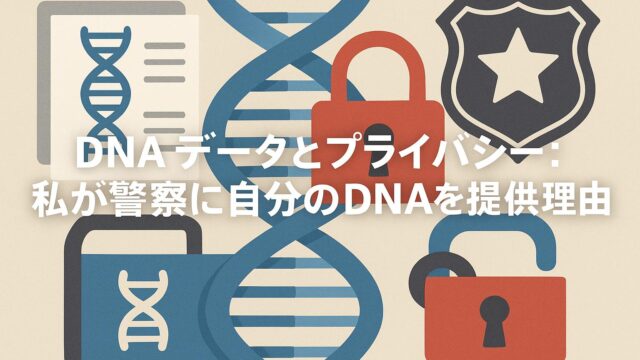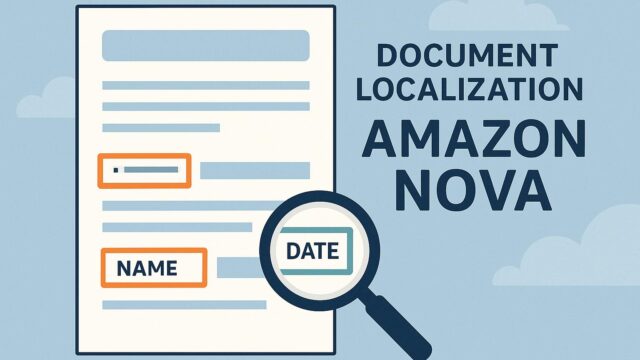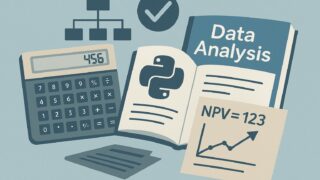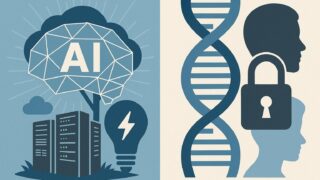- Amazon:
- 楽天:
Deep Think with Confidenceとは何か
日々の意思決定や問題解決では、「深く考える」ことと「その結論にどれだけ自信があるか」をセットで扱うことが成果を左右します。Deep Think with Confidenceとは、単に思考量を増やすのではなく、必要な場面でだけ思考を深め、同時に自分の確信度(自信)を定量・可視化して意思決定の質を高めるアプローチです。過剰な自信で突き進むことも、慎重すぎて動けなくなることも避け、妥当な根拠に裏づけられた判断へ導くための実践的なフレームだと捉えてください。
なぜ「深い思考」と「自信の可視化」をセットにするのか
- 品質向上:結論と根拠、リスク、代替案を明示しやすくなる
- スピード最適化:重要度や不確実性が高い案件だけを深掘りできる
- チームでの合意形成:自信スコアを共有することで議論が建設的に
- 再現性と学習:意思決定ジャーナルにより振り返り・改善が進む
3つの原則:分解・エビデンス・キャリブレーション
1) 分解:問題を小さな論点に切り分け、不確実性の源(情報不足、仮定の強さ、外部依存)を特定します。2) エビデンス:仮説→検証→更新のサイクルで、根拠の質(一次情報か、再現性はあるか)を吟味します。3) キャリブレーション:自分の「自信◯◯%」という感覚と実際の正答率のズレを測り、近づけていきます。たとえば「70%と言ったときは10回中7回当たる」状態を目指します。
実務で使えるフレーム
STEP0 目的と評価指標:成功の定義、制約、意思決定期限を決めます。
STEP1 ファーストアンサー:2分で暫定結論を言語化。
STEP2 自信スコア:結論に対する自信を0.0〜1.0で記録し、根拠と不安要因を箇条書き。
STEP3 深掘りトリガー:自信がしきい値以下、影響が大、論点の競合が強いときだけ深掘り。
STEP4 深掘りチェックリスト:分解→情報収集→反証(自分の結論に不利な証拠探し)→代替案比較→小さな実験。
STEP5 決定・検証ログ:意思決定ジャーナルに「結論・自信・根拠・反証・振り返り予定日」を残します。
AI活用編:LLMと自信の扱い
- プロンプト例:「結論」「根拠(出典または検算)」「前提」「自信スコア(0〜1)」「不確実性要因」を必ず出力するよう指示する
- 選択的思考:難易度推定や迷いが大きい設問だけ思考ステップを長くする(簡単な設問は短く)
- 検証ループ:計算は二系統で検算、事実は出典を要請、複数サンプルの合意率で自信を補助
- 「わからない」を許す:無理に断定させず、追加データ要求やリサーチタスクに切り替える
チーム導入のコツ
- レビュー時は「結論」「自信」「主要根拠」「代替案」「残リスク」の5点セットで提出
- Confidence Readiness Level(CRL):CRL1=アイデア、CRL2=根拠収集中、CRL3=反証済み、CRL4=実験済み、CRL5=本番準備完了、のように段階を明確化
- ダッシュボード化:案件ごとの自信推移と根拠更新履歴を可視化して透明性を高める
よくある落とし穴と対策
- 過剰自信:ベースレート(一般的な確率)を参照、反証者を指名する
- 疑心暗鬼:成功条件を前もって定義し、十分な根拠が揃ったら実行へ
- 無限深掘り:タイムボックス(例:25分)、費用対効果で打ち切り基準を設定
- 根拠の質不足:一次情報の取得、データの出所と検証方法を明記
すぐ使えるテンプレ
自信スコア文例:「本結論の自信は0.62。根拠はA/B/C。不確実性は市場データの更新遅延。追加検証はサンプルN=50のテスト」。
反証質問:「この結論が間違っているとしたら、どの事実が欠けているか?」。
1枚サマリー:「結論」「自信」「根拠」「代替案」「残リスク」「次の一手」。
おすすめの道具と書籍
深い思考を支えるのは、結局は「書き出す」ことと「時間の区切り」です。紙のノートとペン、使いやすいタイマーがあれば、思考の質は大きく変わります。特に『イシューからはじめよ』は、論点を見極め深掘りすべき場所を選ぶ力を養うのに最適です。以下のリンクからチェックしてみてください。
- Amazon:
- 楽天: