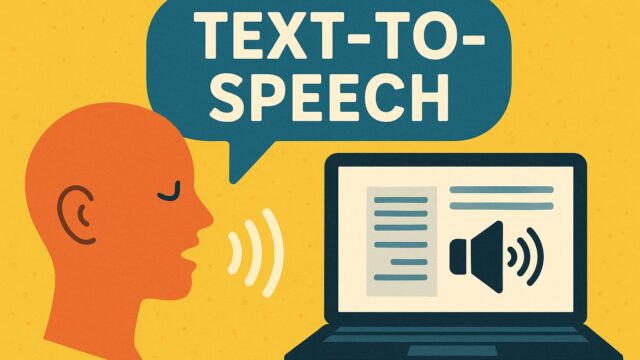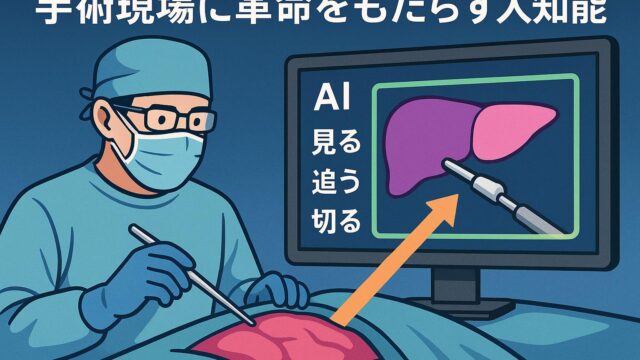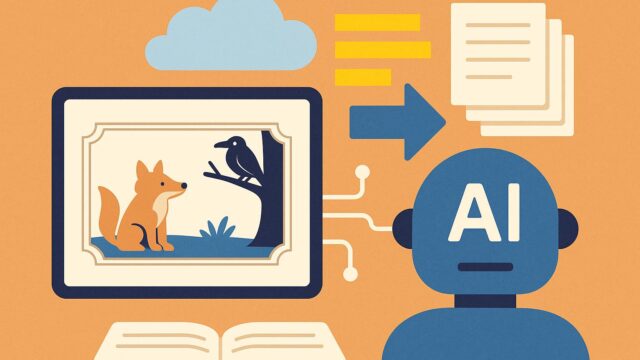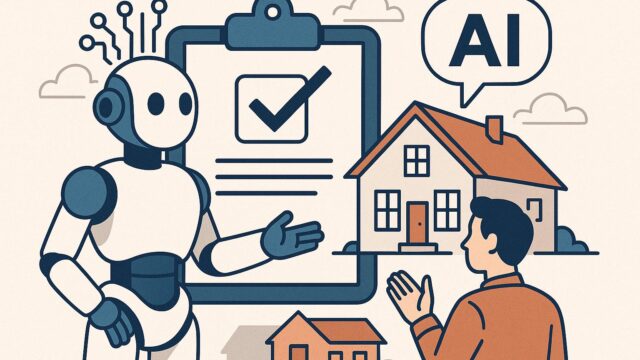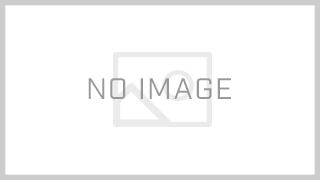- Amazon(ユーザーストーリーマッピング): https://www.amazon.co.jp/dp/4873117366?tag=aizine-22
- Amazon(Designing Bots): https://www.amazon.co.jp/dp/1491974826?tag=aizine-22
- 楽天(ユーザーストーリーマッピング): 楽天で探す
- 楽天(Designing Bots): 楽天で探す
料理人・バイヤーの“知りたい”に即答する──Tyson Foodsの挑戦
食材やメニューの選定は、現場のスピードが命です。にもかかわらず、多くの食品関連サイトでは、検索キーワードを何度も試し、PDFの仕様書を横断し、問い合わせに時間をかける…そんな体験が当たり前でした。Tyson Foodsはこの常識を見直し、AIを活用した会話型の検索アシスタントで、顧客が自然言語で質問すれば、その場で最適な商品や根拠情報にたどり着ける体験へと磨き上げました。
ポイントは「会話×検索×ナレッジ」をつなぐこと
会話アシスタントの肝は、単なるチャットではありません。あいまいな表現や業務の文脈(例:アレルゲン配慮、調理オペレーション、提供シーン、発注単位)を理解し、裏側で確かな根拠に基づく検索と要約を実行できることです。AWSのブログでは、こうした体験を実現するために、検索エンジンと大規模言語モデル(LLM)を連携し、商品仕様、レシピ、よくある質問、販売資料などのナレッジを横断して回答を生成するアプローチが紹介されています。いわゆるRAG(Retrieval-Augmented Generation)を用いることで、最新かつ正確な情報に裏打ちされた応答が可能になります。
会話型検索の代表的なアーキテクチャ(考え方の例)
- インデクシング:商品仕様書、レシピ、Webページ、PDF等を検索エンジンに収集・正規化して索引化。更新フローを自動化して、鮮度と品質を担保。
- 自然言語インターフェース:ユーザーの質問を意図(インテント)に分解し、必要なら追加確認を挟みながら、最小限のステップで目的に誘導。
- RAGパイプライン:問い合わせに関連する根拠文書を検索で取得し、LLMが根拠に基づいて要約・整形。根拠リンクを併記し、透明性を確保。
- 安全性・ガードレール:ドメイン外の質問や曖昧さが残る場合は、追質問や人間の担当者へのエスカレーションに切り替え。
現場価値に直結するユースケース
- アレルゲン・栄養情報の即時確認:ピーナッツ、グルテン等の除外条件を会話で伝え、対象商品だけに絞り込み。
- 利用シーンからの逆引き:大量調理、デリバリー、学食などの前提を一言添えて最適な規格・形態を提示。
- レシピ・活用提案:既存メニューとの相性やオペレーション負荷を加味した提案により、検討の手戻りを削減。
- 調達・在庫連携:ケース単位やリードタイムなど、発注の前提情報を会話で補完して意思決定を早める。
導入成功の勘所:データ、体験、運用を三位一体で
- データ基盤を整える:仕様書の表記ゆれやバージョン違い、PDFのテキスト化、メタデータの標準化に先手を打つ。
- 会話設計を磨く:よくある質問からインテントを設計し、追質問・確認・提示フォーマット(表・箇条書き・カード)をテンプレ化。
- 根拠提示を徹底:回答と一緒にソースのリンクや抜粋を提示し、現場が安心して使える体験にする。
- 評価と改善のループ:検索成功率、会話の自己解決率、離脱箇所、意図不明ログを定点観測し、用語辞書・プロンプト・データを継続改善。
スモールスタートの進め方
まずは限定されたカテゴリ(例:主力商品のみ、特定の業態)で試行し、FAQと仕様書を中心にRAGを組み立てます。応答は常に根拠リンク付きにし、判断が分かれる質問は人による最終確認へ。初期はWeb上の会話ウィジェットとして公開し、評価が進んだら検索ボックスそのものを会話インターフェースに置き換えると、自然な浸透が期待できます。
責任あるAIの観点
- 正確性:特にアレルゲンや栄養など安全性に直結する情報は、根拠の最新版へのリンクと免責の表現をセットで提示。
- プライバシー:顧客や取引先の特定情報を扱う場合、保存・学習のスコープにガードレールを設定。
- バイアス抑制:モデル応答が特定商品を過剰に推しすぎないよう、提示基準と透明性を設計。
チェックリスト(すぐ始められる)
- 検索対象の文書・データソースを棚卸しし、更新頻度と品質を評価したか。
- トップ20の質問シナリオに対して、会話フローと期待出力を定義したか。
- 回答と根拠リンクの並列表現(カードUIなど)を用意したか。
- 人のサポートへのハンドオフ動線と、会話ログの改善フィードバックを設計したか。
まとめ:検索は「聞ける化」で生まれ変わる
Tyson Foodsの取り組みが示すのは、検索を「聞ける化」するだけで、顧客は迷わず、現場は速く、企業は学び続けられるということ。会話、検索、ナレッジをつないだ体験は、食品に限らず、B2Bの複雑な意思決定に強力に効きます。小さく始めて学び、根拠提示と安全性を徹底する──これが成功の最短ルートです。
- Amazon(ユーザーストーリーマッピング): https://www.amazon.co.jp/dp/4873117366?tag=aizine-22
- Amazon(Designing Bots): https://www.amazon.co.jp/dp/1491974826?tag=aizine-22
- 楽天(ユーザーストーリーマッピング): 楽天で探す
- 楽天(Designing Bots): 楽天で探す